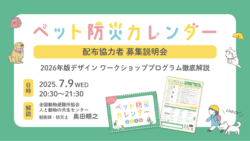■不動産の遺贈寄付は要注意
動物たちのために遺産を活用したい。その気持ちがあっても、きちんと制度を理解しなければ、適切な寄付はできません。特に不動産を含む遺贈は注意が必要です。
遺贈には、包括遺贈や特定遺贈の2種類がありますが、包括遺贈であれ、特定遺贈であれ、不動産や株式などの現物寄付を行う場合には注意が必要です。それは、公益のために寄付しているにも関わらず、寄付した遺贈者やその法定相続人に「みなし譲渡所得税」と呼ばれる所得税が課税されることがあるからです。
「みなし譲渡課税」とは、不動産などの資産を低価格あるいは無償で法人に譲渡した際に、その譲渡があたかも売却されたかのように見なされて、所得税が課税される制度です。たとえば、個人が所有する不動産を法人に寄付した場合、その時点での時価と購入時の価格との差額(=含み益)に対して所得税がかかります。具体的には、800万円で購入した不動産が現在の時価で2000万円の場合、その差額である1200万円の含み益が生じます。この含み益に対して課税されるということです。所得税と地方税を合わせると税率は約20%になりますから、1200万円×約20%=約240万円を所得税として納税しなくてはなりません。包括遺贈を選択された場合、包括遺贈を受けた受遺者に納税義務がありますから、遺贈を受けた法人に240万円の納税義務が生じます。
不動産の購入金額がわかる場合はまだ良いですが、契約書がないなどの理由で、購入金額の証明が難しい場合、時価の5%のみが購入金額として認められます。つまり 契約書がない場合、時価の95%が含み益と判断されるため、より多くのみなし譲渡所得税が課税されることになります。
「現預金はほとんどないけど、親から譲り受けた土地・建物があるから、遺贈寄付で活用してもらいたい」と考えたとしても、その土地・建物の時価が高ければ高いほど、含み益も大きくなり、納税額も大きくなります。土地・建物と一緒に遺贈した現預金がすべてみなし譲渡課税でなくなってしまう、あるいは、遺贈した現預金では納税の支払いには足りず遺贈を受けることができないといった事態になる可能性があります。
特定遺贈を選択した場合は、受遺者である法人に納税義務はありませんが、法定相続人にみなし譲渡課税の納税義務が生じるため、法定相続人は、受け取る遺産が減った上に納税義務まで生じることとなります。法定相続人と受遺者の間でトラブルになる可能性があり、十分に注意が必要です。
このような制度があるため、多くの団体で、現預金以外の不動産や有価証券を含む包括遺贈については、受け入れを行っていないのが現状です。
超高齢社会の中で、身寄りのない高齢者の数はますます増えています。長年、動物と暮らしてきて、動物たちのために遺産を活用したいと考える人も少なくありません。そして、そのように考え、遺贈寄付を準備していただける方は、比較的裕福な方が多く、財産として不動産も所有していることがほとんどです。「みなし譲渡課税」の制度は、そうした方が、遺産を公益のために活用する上で、障壁となる制度になっています。
■不動産の遺贈寄付を実現する方法
不動産を含む財産を包括遺贈したいという希望は少なくありません。実際、当団体への遺贈寄付の相談のうち半数以上は、不動産を含めた包括遺贈の相談です。
そもそも持ち家に暮らしている場合、生前に売却し整理しておくのが難しいケースは少なくないでしょう。このようなケースでは、どうしても相続財産の中に不動産が含まれることになります。相続財産全体のうち約4割は不動産であるため、ほとんどの相続で不動産の処理の問題が出てくることとなります。
動物のための遺贈寄付を実現するためには、不動産の遺贈の問題をクリアすることが不可欠です。そこで当団体では、税理士、弁護士、行政書士、不動産の専門家などと連携して、不動産や株式などの有価証券も含めた包括遺贈を受けられる体制づくりを行い、また、当団体への寄付だけでなく、ほかの動物関連団体への寄付の接続も想定した「動物のための遺贈寄付相談窓口」を設置しています。現在1~2カ月に1件程度、具体的な遺贈寄付の相談について対応しています。
不動産を含む包括遺贈による遺贈寄付を実現するには、主にふたつの方法があります。ひとつが不動産を現金化してから寄付を行う方法、もうひとつが、みなし譲渡所得税の非課税特例を受ける方法です。
◎不動産を現金化してから寄付する方法
不動産を現金化してから寄付をすれば、寄付を受ける団体側としては、特に問題はありません。団体としては非常にありがたい方法です。
不動産を現金化してから寄付するためには、遺言書を作成し、不動産を売却した上で現金を寄付するよう指示を記しておく必要があります。たとえば「○○市所在の土地および建物を売却し、その売却代金の全額を△△NPOに寄付する」といった具体的な内容を明記するとともに、遺言執行者を指名しておきます。遺言執行者が決まっていないと、売却の手続きにおいて、登記などの面で余計な手間が発生します。遺言執行者について、弁護士や行政書士等の専門家に頼む場合は、遺言執行に関わる報酬を支払う必要があります。不動産を売却してからの遺贈となるとそれだけ事務負担が大きくなりますので、報酬の額についても、売却がない場合に比べて大きくなることがあります。
不動産を売却するには、登記名義の確認や境界の調査、固定資産税評価額の確認など、事前の準備が必要です。売却活動そのものは不動産会社に仲介を依頼して進めるのが一般的ですが、事前準備に始まり、買主の募集から売却完了までには、早くても1カ月程度、通常は数カ月以上を要します。売却代金を得た後、その現金を寄付先に送金することで、寄付は完了します。
不動産を売却して現金化するということは不動産売買に関するそれなりの知識と経験が必要不可欠です。不動産売買では、一般的に早く売ろうとすればするほど、売買代金が低くなります。逆に、不動産の相場や、当該不動産の状態ならどの程度で売れるかなどの見通しがあり、ある程度時間をかけることができれば、適正な値段での取引が可能になります。遺言執行者が相続手続きと遺贈寄付を進めるために、できるだけ早く現金化したいと考えてしまうと、本来の不動産の価値よりも大分低い価格での取引となる可能性があります。
このような背景を考えると、不動産取引の経験の少ない親族に遺言執行者を頼むよりも、不動産売買の知識が十分にあり、宅建業者との連携も含めてネットワークがある専門家に遺言執行者になってもらうように頼むほうが、何かと手間が省け、現金化や寄付についてもスムーズに行えると考えたほうが良いでしょう。
不動産を現金化して寄付する場合、売却にかかる税金や諸経費を引いた上で寄付することになるため、不動産そのものを現物寄付する場合に比べて、寄付できる財産の総額自体は小さくなります。先に挙げたように購入時の契約書がない場合は、販売した取引価格の95%が含み益とみなされるため、その20%ほどを税金として納めなければならなくなります。仲介手数料なども含めれば、寄付できる額は本来の不動産の価値の4分の3程度になるわけです。また、不動産取引の知識のある専門家に頼んだ場合であっても、ある程度は、不動産の売却を急がなければならないため、通常の不動産売買に比べて売却価格が低くなってしまうことはあるでしょう。
そもそも現金化するといっても、不動産の中には、売れない不動産、いわゆる、「負動産」が含まれる場合があります。売れない山を持っている、長年空き家で放置した田舎の土地を持っているという場合、売るのではなく、引き取ってもらうという対応が必要になってくるでしょう。「負動産」の処分は、売れる不動産の処分に比べて難易度が非常に高くなります。生前に処分をするか、「負動産」を扱える専門の団体に入ってもらう必要があることを頭に入れておきましょう。
◎みなし譲渡所得税の非課税特例を受ける方法
もうひとつの方法が、「現物寄附のみなし譲渡所得税等の非課税特例」と呼ばれる制度です。この制度は、公益法人等に対し現物寄付を行った時に、特定の条件に該当すれば、みなし譲渡課税について免除を受けることができる制度です。
この制度は、寄付金に関する税制優遇を受けている、学校法人や公益財団法人等が対象でしたが、2020年に認定NPO法人も対象となりました。税制優遇を受けているすべての法人が使えるわけではなく、一定の要件を満たすと所轄庁が認めた基金を設置し、遺贈を受けた不動産などを基金に組み入れる場合にのみ適用されます。
認定NPO法人であっても、その法人の中に、一定の要件を満たすと所轄庁が認めた基金を設置していなければ利用することはできません。ただでさえ、認定NPO法人はNPO法人全体の2・6%しかありませんが、その中でも、所轄庁に認められた基金を設置している法人は、さらに少ないのが現状です。
その上、基金に組み入れられた財産は、特定の公益目的にのみに直接活用することとされています。基金に組み入れた不動産を売却し現金化して団体の活動に充てることはできません。不動産を売却して現金化したり、賃貸して収益を得たりする場合はこの特例の対象外となり、課税が発生します。
ここでいう「公益目的に直接用いる」とは、たとえば団体の事務所や保護施設として使用する場合を指します。当団体の場合、ペット後見の支援拠点を全国に増やしており、寄付を受けた不動産について、事務所兼保護施設として利用することを想定しています。しかし実際には、不動産の立地条件や用途制限により動物用の保管施設(畜舎)を設置できない場合があり、事務所や保護施設としての活用が難しいケースも存在します。
このような事情を踏まえると、みなし譲渡課税の非課税特例を利用するためには、実際に寄付先の団体に相談して、どのような活用を想定しているか、また、法律的に想定している活用方法が可能かということを確認する必要があります。
当団体の場合、保護施設としての活用ができない不動産については、生活困窮ペット飼育者向けの住宅としての活用を想定しています。当団体では居住支援法人としての指定を受け、生活困窮者や高齢者がペットとともに暮らせる住まいを提供しています。団体所有の賃貸物件を安価で提供し、行き場のないペットと飼い主の支援にも取り組んでいます。寄付を受けた不動産について、事務所や保護施設として使えない場合でも、生活困窮ペット飼育者の支援に直接充てるという形であれば、公益目的に活用しているため、非課税特例を受けることができます。
このように、みなし譲渡所得税の非課税特例は、使用する上で非常に制約の強い制度となっています。非課税の特例は公平性の観点からそれだけ厳しいものにしなければならないということなのでしょう。
厳しいからと言って使えないわけではありません。しっかりと準備をすることで使える制度です。当団体では、不動産を含む遺贈寄付の枠組み作りを目指し、2022年にペット後見基金を設置し、一定の要件を満たす基金であるとして、岐阜県の承認を得ることができました。2025年現在、この基金を活用して、全国でのペット後見の受け皿づくりを目指して、現物寄付を含めた寄付を募集しています。
このような制度を活用した寄付の受け皿作りは、多くの団体が準備できるものではありませんので、当団体が受け皿となり、全国の動物関係団体と連携して、ペット後見の仕組みと、遺贈寄付による資金循環作りを進めていきたいと考えています。